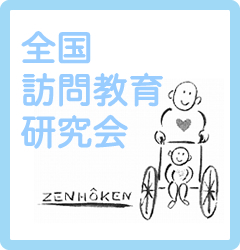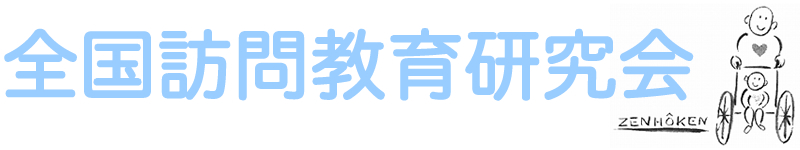訪問教育の現状と課題Ⅷ 500円
2017年に全訪研が行った訪問教育に関する第八次全国調査の報告書です。
学習指導要領には「実情に応じた授業時数を適切に定める」と書かれていますが、授業時数だけでなく、スクーリングや複数訪問など、教育内容の充実が難しい状況が明らかになりました。子どもたちの多様なニーズに対応する訪問教育のあり方を検討していく必要があります。

訪問教育の現状と課題Ⅶ 500円
2013年に全訪研が行った訪問教育に関する第7次全国調査の報告書です。
依然として、訪問授業の回数・時間数は増えていませんが、4年間での変化として、病院訪問、施設訪問での授業回数・時間数が多様になっていることが分かりました。また、学校における医療的ケアの教員実施が法的に認められたことによる教育条件の変化も明らかになっています。
「訪問教育の現状と課題Ⅵ」と比べていただくと、訪問教育の今が見えてきます。

訪問教育の現状と課題Ⅵ 500円
2009年に全訪研が行った訪問教育に関する第6次全国調査の報告書です。
訪問授業の回数・時間数が通学籍に比べて、圧倒的に少ないことが分かります。授業づくりやスクーリング、行事などの参加など、全国の先生方が工夫していること、子どもたちや保護者、教員の願いなどが伝わってきます。

せんせいが届ける学校 1,600円
訪問教育を初めて担当する先生方は、学校を離れて子どもと1対1で向き合うことに戸惑いを覚えるのではないでしょうか。障害や疾病により通学することが難しい子どもたちに学校を届けることの意味や授業づくりなどをわかりやすく説明しています。重症児教育の入門書としてもお使いいただけます。
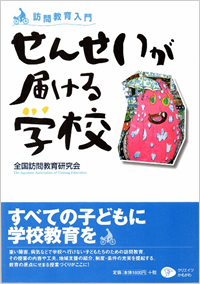
訪問教育研究
全訪研の研究収録です。各年度の全国大会の記念講演、分科会まとめ、発表レポート、訪問教育に関する資料が掲載されています。
訪問教育研究第35集 1,000円
○大会シンポジウム「訪問教育と医療的ケア~その歴史と課題~」
下川和洋(NPO法人地域ケアさぽーと研究所)
加藤亜里沙(和歌山医療的ケアを必要とする子どもの教育と生活を考える会家族部会紀いけあ会員)
縄田登紀子(大阪府立藤井寺支援学校 教頭)
和田聖子(一般社団法人「幹」管理者統括 看護師)
○訪問教育研究資料
・特別支援教育に関する資料
・医療的ケアの必要な方の地域生活を支える取り組み
・障害者の生涯学習関連施策リンク集
訪問教育研究第34集 1,000円
○大会シンポジウム「障害の重い人たちの生涯学習~訪問卒業生のいのち輝く学びをめざして~」
岩井正一(愛媛県重症心身障害児者) を守る会、西園健三(ユースコラ鹿児島社会福祉法人麦の芽)
栗山弘子(居宅訪問型児童発達支援「いるか」シンポジスト
苅田知則・樫木暢子(訪問カレッジ・オープンカレッジ@愛媛大学:教育学部)
○訪問教育研究資料
・訪問教育に関する資料
・医療的ケアの必要な方の地域生活を支える取り組み
・重い障害のある児者への支援
訪問教育研究第33集 1,000円
○大会シンポジウム「コロナ時代の訪問教育~現状と課題~」
南 有紀(和歌山県立紀北支援学校)、中野久枝(東京都立墨東特別支援学校)
早野節子(特定非営利活動法人かすみ草)、樫木暢子(愛媛大学)
〇訪問教育研究資料
・特別支援教育に関する資料
・医療的ケアの必要な方の地域生活を支える取り組み
・重い障害のある児者への支援
訪問教育研究第32集 1,000円
○大会記念講演「要医療児の育ちと暮らし ~子どもたちから学ぶ大切なこと~」
那須康子(埼玉医科大学総合医療センター小児科講師・埼玉医大福祉会カルガモの家兼務)
〇訪問教育研究資料
・特別支援教育に関する資料
・医療的ケアの必要な方の地域生活を支える取り組み
・重い障害のある児者への支援